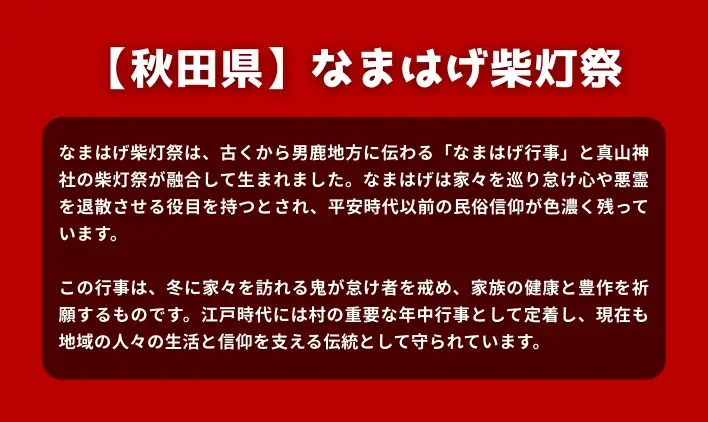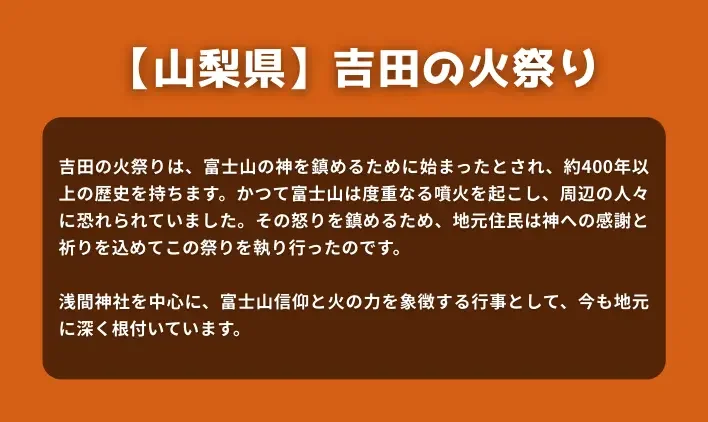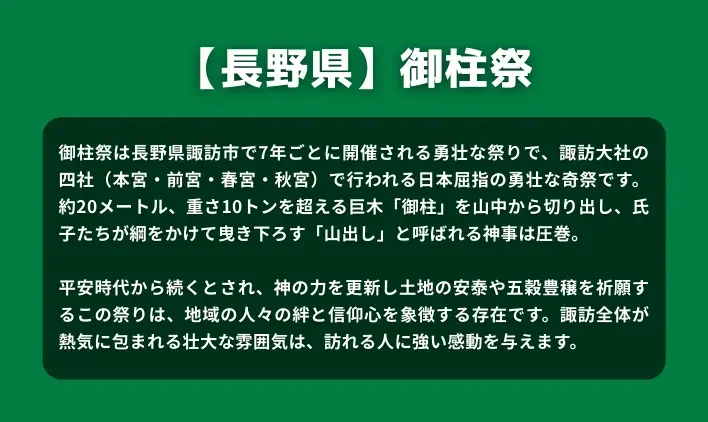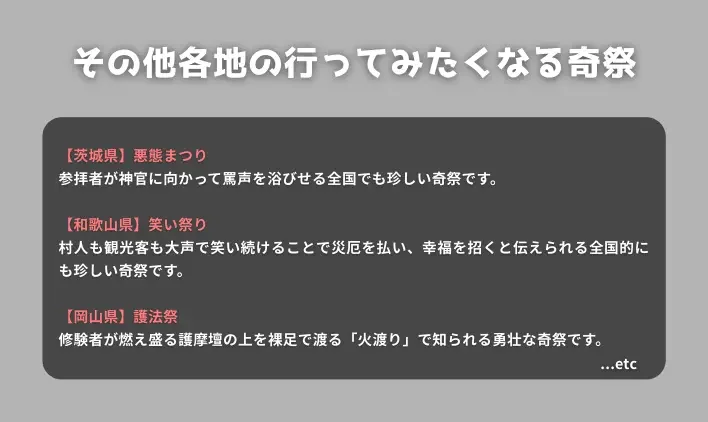日本三大奇祭とは?歴史や行事内容とあわせて行ってみたくなるその他各地の奇祭もご紹介!
リゾートバイトお役立ち情報2025/10/09
最終更新日:2026/02/05
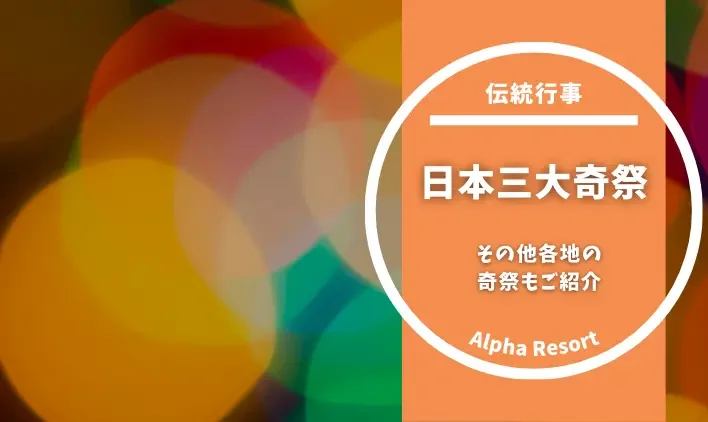
日本各地には古来から受け継がれてきた、独特で迫力ある「奇祭」と呼ばれる祭りが数多く存在します。特に有名なのが「日本三大奇祭」と称される秋田県のなまはげ柴灯祭、山梨県の吉田の火祭り、長野県の御柱祭です。
いずれも地域の信仰や歴史を色濃く映し出し、見る者を圧倒する壮大な儀式が魅力。本記事では三大奇祭の歴史や見どころを詳しく解説するとともに、行ってみたくなる全国各地の奇祭も併せてご紹介します。
奇祭とは
奇祭とは、地域独自の歴史や信仰を背景に、一般的な祭りとは一線を画す独特な風習や儀式を行う祭礼のことです。日本各地には、古来より続く神事や伝説をもとに、勇壮さや奇抜さを備えた多様な奇祭が存在します。
豊作祈願や悪霊退散、無病息災など目的はさまざまで、非日常的な雰囲気と迫力ある演出が人々を魅了し続けています。奇祭は単なる娯楽ではなく、地域の精神文化を色濃く反映した貴重な伝統行事であり、訪れることでその土地ならではの信仰や歴史を体感できるでしょう。
最もよく聞く「日本三大奇祭」とは
数ある奇祭の中でも特に有名なのが「日本三大奇祭」と呼ばれる秋田県のなまはげ柴灯祭、山梨県の吉田の火祭り、長野県の御柱祭です。いずれも古い歴史を持ち、勇壮かつ独特の儀式が行われます。以下では各祭りの歴史や行事内容、関連施設などを詳しく紹介します。
【秋田県】なまはげ柴灯祭
なまはげ柴灯祭は、秋田県男鹿市の真山神社で毎年2月の第2金・土・日曜日に行われる冬の風物詩で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。鬼の面をつけた「なまはげ」が、山から下りてくる姿は迫力満点。
家々を巡って怠け心を戒め、無病息災や五穀豊穣を祈ります。民俗信仰と迫力ある演出が融合した、秋田を代表する伝統行事として多くの観光客を魅了しています。
歴史
なまはげ柴灯祭は、古くから男鹿地方に伝わる「なまはげ行事」と真山神社の柴灯祭が融合して生まれました。なまはげは家々を巡り怠け心や悪霊を退散させる役目を持つとされ、平安時代以前の民俗信仰が色濃く残っています。
この行事は、冬に家々を訪れる鬼が怠け者を戒め、家族の健康と豊作を祈願するものです。江戸時代には村の重要な年中行事として定着し、現在も地域の人々の生活と信仰を支える伝統として守られています。
行事内容
祭りでは、松明を持ったなまはげが山から下り、太鼓の音と共に参道を進みます。境内では神楽や祈祷が行われ、幻想的な炎と雪景色が相まって荘厳な雰囲気を演出。なまはげは観客にも近づき、悪い心を戒めるような迫力ある所作を見せます。
参加者はその迫力に圧倒されながらも、邪気を祓い家内安全を願うことができます。夜空に舞う火の粉や鬼の叫び声が響く様子はまさに圧巻です。
基本情報
会場は男鹿市の真山神社で、雪深い時期のため防寒対策が欠かせません。最寄り駅からはシャトルバスが運行され、夜間は冷え込みが厳しいので、厚手の防寒具や滑りにくい靴が必須になります。
また、祭り期間中は周辺の宿泊施設が混み合うため、早めの予約がおすすめ。観覧席は有料エリアもあり、迫力ある儀式を間近で体感するなら、事前チケットの確保が安心です。
【真山神社の基本情報】
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢 |
| 電話番号 | 0185-24-9220 |
| アクセス |
- JR男鹿駅よりなまはげシャトルで約25分 - 昭和男鹿半島I.Cより車で40分 |
| 料金 |
入場協賛金 1,000円 中学生以下無料 ※事前入場申込制(各日上限2,000人) |
| 開催期間 | 毎年2月第2金、土、日曜 |
| 開催時間 | 18:00~20:30 |
| 公式サイト | https://oganavi.com/sedo/ |
なまはげ柴灯祭の関連施設
男鹿真山伝承館では、なまはげの衣装や道具を間近に見ながらその起源や文化を学べます。また、隣接するなまはげ館では一年を通して面や衣装の展示、映像資料で祭りの迫力を体感可能です。
実際の行事を見逃しても、これらの施設で祭りの雰囲気を味わうことができます。地域の民俗文化や歴史を深く知りたい人には必見のスポットです。
【男鹿真山伝承館の基本情報】
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢 |
| 電話番号 | 0185-22-5050 |
| アクセス |
- JR「男鹿駅」よりタクシー・なまはげシャトルで約20分 - 昭和男鹿半島I.Cより車で約40分 |
| 料金 |
大人 1,100円 小中高生 660円 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 定休日 | なし |
| 公式サイト | https://namahage.co.jp/namahagekan/ |
【山梨県】吉田の火祭り
山梨県富士吉田市で毎年8月26日・27日に行われる「吉田の火祭り」は、富士山の噴火鎮静を祈願して始まった400年以上の歴史を持つ伝統行事です。町の通りに高さ約3メートルの大松明が約70基立ち並び、夜になると一斉に点火されます。
無数の炎が闇を照らし、太鼓や神輿の練り歩きとともに荘厳かつ幻想的な雰囲気を演出。富士山信仰と火の神秘を感じられる奇祭です。
歴史
吉田の火祭りは、富士山の神を鎮めるために始まったとされ、約400年以上の歴史を持ちます。かつて富士山は度重なる噴火を起こし、周辺の人々に恐れられていました。その怒りを鎮めるため、地元住民は神への感謝と祈りを込めてこの祭りを執り行ったのです。
浅間神社を中心に、富士山信仰と火の力を象徴する行事として、今も地元に深く根付いています。
行事内容
町の通りには、高さ約3メートルもの大松明が立ち並び、夜になると一斉に火が灯されます。無数の炎が揺らめく光景は圧巻で、観客はまるで炎の海に包まれたかのような迫力を体験できます。
神輿の練り歩きや太鼓演奏が祭りをさらに盛り上げ、富士山の雄大な姿を背景に行われるその光景は神秘的です。地元住民や観光客が一体となり、古来の祈りを現代に伝えています。
基本情報
開催日は毎年8月26日・27日。会場は富士山北麓に位置する富士吉田市中心部で、最寄り駅は富士急行線の富士山駅。夜間は涼しくなるため軽い上着を持参すると安心です。
周辺には観光施設や宿泊施設が充実しており、早めの予約が必要です。大松明の点火は夜8時頃から始まるため、日没後の移動計画を事前に立てておくと快適に楽しめます。
【吉田の火祭りの基本情報】
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県富士吉田市上吉田諏訪(北口本宮冨士浅間神社周辺) |
| 電話番号 | 0555-21-1000 |
| アクセス |
- 富士急行「富士山駅」より徒歩約5分 - 中央道河口湖ICより車で約10分 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年8月26日、27日 |
| 開催時間 |
神事は各日午後から 松明点火は26日18:30〜22:00 |
| 公式サイト | https://www.sengenjinja.jp/himatsuri/index.html |
吉田の火祭りの関連施設
北口本宮冨士浅間神社は祭りの中心地で、富士山信仰の歴史を感じられます。また、富士山世界遺産センターでは、富士山の成り立ちや噴火の歴史を学べ、祭りの背景を理解するのに役立ちます。
周辺には富士五湖観光もあり、祭りと合わせて訪れることで富士山エリアをより深く体感できます。
【北口本宮冨士浅間神社】
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県富士吉田市上吉田5558 |
| 電話番号 | 0555-22-0221(社務所) |
| アクセス |
- 富士急行線「富士山駅」より徒歩約20分 - 中央自動車道河口湖I.C.より車で約10分 |
| 拝観料 | 無料 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00(季節により変動あり) |
| 公式サイト | https://sengenjinja.jp/ |
【長野県】御柱祭
御柱祭は長野県諏訪市で7年ごとに開催される勇壮な祭りで、諏訪大社の四社(本宮・前宮・春宮・秋宮)で行われる日本屈指の勇壮な奇祭です。約20メートル、重さ10トンを超える巨木「御柱」を山中から切り出し、氏子たちが綱をかけて曳き下ろす「山出し」と呼ばれる神事は圧巻。
平安時代から続くとされ、神の力を更新し土地の安泰や五穀豊穣を祈願するこの祭りは、地域の人々の絆と信仰心を象徴する存在です。諏訪全体が熱気に包まれる壮大な雰囲気は、訪れる人に強い感動を与えます。
行事内容
祭りでは、高さ20メートルを超える御柱を数百人もの氏子たちが綱を引きながら急坂を下る「木落し」が最大の見どころです。巨木が轟音とともに坂を滑り落ちる瞬間は迫力満点で、観客は息を呑むほど。
続いて御柱を神社に建てる「建御柱」では、木の上に人が乗りながら慎重に立てていく光景が広がります。参加者と見物客の熱気が一体となり、諏訪全体が祭り一色に染まります。
基本情報
御柱祭は寅年と申年の7年ごとに開催され、諏訪大社の四社(本宮・前宮・春宮・秋宮)で行われます。最寄り駅は上諏訪駅で、期間中は大変混雑するため宿泊予約は早めが安心です。
春の山間部はまだ冷えるため、暖かい服装で訪れると快適に楽しめます。巨大な木を曳く様子は迫力があり、写真撮影にも最適なシーンが数多くあります。
【御柱祭の基本情報】
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪市中洲宮山1(諏訪大社四社:本宮・前宮・春宮・秋宮 各社) |
| 電話番号 | 0266-58-1123 |
| アクセス |
- JR「下諏訪駅」から徒歩約15分(下社秋宮) - 中央自動車道諏訪I.C.より車で約15分 |
| 料金 | 基本無料(一部観覧席のみ有料) |
| 開催期間 | 7年ごと(寅年・申年)の4月〜5月 |
| 開催時間 | 木落し・建御柱など日程により異なる |
| 公式サイト | https://www.onbashira.jp/ |
御柱祭の関連施設
諏訪大社本宮や上社前宮では、祭りの歴史や神事を間近で体感できます。また、諏訪市博物館では御柱祭に関する資料や映像展示があり、開催期間外でも祭りの雰囲気を感じられます。
湖畔の諏訪湖エリアには温泉や宿泊施設も豊富で、観光と合わせて楽しむことができます。
【諏訪市博物館の基本情報】
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪市中洲171-2(諏訪大社上社本宮前) |
| 電話番号 | 0266-52-7080 |
| アクセス |
- JR中央本線「上諏訪駅」よりバスで約15分、「上社前宮」停留所下車より徒歩約5分 - 中央自動車道諏訪I.Cより車で約10分 |
| 料金 |
一般300円 高校生200円 小中学生150円(特別展は別料金) |
| 営業時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |
| 定休日 |
月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始 |
| 公式サイト | https://www.city.suwa.lg.jp/site/museum/ |
その他各地の行ってみたくなる奇祭
三大奇祭以外にも全国には個性豊かな奇祭が数多く存在します。各地に根付いた独自の風習や文化を知る絶好の機会として、多くの観光客を惹きつけています。
【茨城県】悪態まつり
茨城県笠間市の愛宕神社で毎年12月第3日曜日に行われる「悪態まつり」は、参拝者が神官に向かって罵声を浴びせる全国でも珍しい奇祭です。参加者は「怠け者」「馬鹿者」など思い切った言葉を大声で投げつけ、心に溜まった不満や厄を浄化するとされています。
罵ることで厄払いと無病息災を祈願する独特の風習は江戸時代から続き、祭りの最後には神前で感謝を捧げる厳かな儀式も行われます。
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県笠間市泉字鹿島山(愛宕神社) |
| 電話番号 | 0296-77-1101(笠間観光協会) |
| アクセス |
- JR常磐線「友部駅」よりタクシーで約15分 - 北関東自動車道笠間西I.Cより車で約10分 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年12月第3日曜日 |
| 開催時間 | 午前中〜昼過ぎ |
| 公式サイト | https://www.kasama-kankou.jp/section.php?code=479 |
【和歌山県】笑い祭り
和歌山県日高郡由良町の丹生神社で毎年10月第1日曜日に開催される「笑い祭り」は、村人も観光客も大声で笑い続けることで災厄を払い、幸福を招くと伝えられる全国的にも珍しい奇祭です。氏子や神輿を担ぐ人々が「ワッハッハ!」と豪快に笑いながら町を練り歩き、その笑い声が絶え間なく響き渡ります。
古くから「笑う門には福来る」という言葉が示すように、笑いには邪気を退ける力があると信じられてきました。見る人も自然と笑顔になり、会場全体が温かい幸福感に包まれます。
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県日高郡由良町里(丹生神社) |
| 電話番号 | 0738-65-0200(由良町観光協会) |
| アクセス |
- JRきのくに線「由良駅」より徒歩約20分 - 湯浅御坊道路広川I.Cより車で約15分 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年10月第1日曜日 |
| 開催時間 | 10:00〜15:00頃 |
| 公式サイト | https://hidakagawa-kanko.jp/miru/nyuujinnja/ |
【岡山県】護法祭
岡山県真庭市の木山神社で毎年1月第2土曜日に行われる「護法祭」は、修験者が燃え盛る護摩壇の上を裸足で渡る「火渡り」で知られる勇壮な奇祭です。護法善神への感謝と地域の無病息災・五穀豊穣を祈願するこの祭りは、古くから山岳信仰と深く結びついてきました。
夜空を焦がす炎とほら貝や太鼓の音が響き渡る中、修験者が恐れを見せず炎を進む姿は迫力満点。火を浄化の象徴とする古代信仰を現代に伝える神聖な儀式として、多くの参拝客や観光客を魅了します。
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 岡山県真庭市落合垂水(木山神社) |
| 電話番号 | 0867-52-1111(真庭市観光協会) |
| アクセス |
- JR姫新線「美作落合駅」より車で約15分 - 中国自動車道落合I.C.より車で約10分 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年1月第2土曜日 |
| 開催時間 | 18:00〜21:00頃 |
| 公式サイト | https://www.okayama-kanko.jp/event/detail_12623.html |
【大分県】ケベス祭り
大分県国東市国東町浜の岩戸寺で毎年10月第2土曜日に行われる「ケベス祭り」は、全身を藁で覆った「ケベス」と呼ばれる男が燃え盛る火の中を駆け回る、迫力満点の奇祭です。ケベスは悪霊を払い村に福を呼ぶ神の使いとされ、松明を振りかざしながら境内を走り回ります。
火の粉が舞い、観客は熱気と緊張感に包まれ、古代から続く火祭りの力強さを体感できます。無病息災や五穀豊穣を祈願するこの祭りは、国東半島に残る独特な信仰を今に伝えているのです。
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 大分県国東市国東町浜(岩戸寺) |
| 電話番号 | 0978-72-5168(国東市観光協会) |
| アクセス |
- JR日豊本線「杵築駅」より車で約50分 - 宇佐別府道路宇佐I.C.より車で約60分 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年10月第2土曜日 |
| 開催時間 | 19:00〜21:00頃 |
| 公式サイト | https://x.gd/ViC72 |
【鹿児島県】ヨッカブイ
鹿児島県薩摩川内市の甑島で毎年1月7日前後に行われる「ヨッカブイ」は、鬼に扮した男たちが家々を巡り、住民や子どもたちを驚かせながら悪霊退散と無病息災を祈願する奇祭です。
赤や黒に彩られた面と藁装束を身にまとった鬼たちは、大声を上げて村を練り歩き、家々に幸運をもたらすとされます。子どもたちは恐怖に泣きながらも、鬼に触れられることで厄が落ちると伝えられ、島全体が熱気に包まれる独特の雰囲気を楽しめます。
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県薩摩川内市里町(甑島) |
| 電話番号 | 09969-6-3930(甑島観光案内所) |
| アクセス |
- 川内港より甑島行きフェリーで約80分 - 里港下船後徒歩圏内 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年1月7日頃 |
| 開催時間 | 夕刻〜夜 |
| 公式サイト | https://www.kagoshima-kankou.com/event/20375 |
【沖縄県】パーントゥ
沖縄県宮古島市島尻地区で毎年旧暦9月に行われる「パーントゥ」は、全身を泥で覆った神が村中を歩き回り、人々や家々に泥を塗りつけて厄払いと豊作祈願を行う独特の奇祭です。泥を塗られた人は健康や子宝に恵まれるとされ、地元住民だけでなく観光客にも歓迎されます。
神々は笑い声と歓声に包まれながら練り歩き、村全体が一体となる雰囲気は圧巻。南国ならではの自然信仰と人々の祈りが感じられる貴重な伝統行事として、多くの来訪者を魅了しています。
アクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良島尻地区 |
| 電話番号 | 0980-73-2690(宮古島観光協会) |
| アクセス | - 宮古空港より車で約20分 |
| 料金 | 無料 |
| 開催期間 | 毎年旧暦9月(新暦10月頃、日程は年により変動) |
| 開催時間 | 日中〜夕刻 |
| 公式サイト | https://x.gd/VfVx6 |
奇祭を楽しむならリゾートバイトがおすすめ!
奇祭は地域によって開催時期や場所が異なり、長期滞在して楽しむのに最適です。リゾートバイトを利用すれば滞在費を抑えつつ、現地の人々と交流しながら文化を深く体感できます。観光客として訪れるだけでなく、地域の一員として祭りに関わることで、より濃密で特別な体験が得られるでしょう。